
ブログ Blog
「コミュニティをつりたい」と願うならば
先週、原村で開催された「愛と平和の祭典2025」の講演会を終えてから、
「コミュニティとは何ぞや」
という問いに自問自答を繰り返しています。
(そうなのよ、わたし、意外と真面目なのよね~)

そもそも「コミュニティ」って、
単に「人が集まっている場所」ではなく、「そこに人と人との関係性や一体感がある集まり」のことらしい。
語源はラテン語の communis(共有の・共通の)で、「共に持つ」。
面白いことに、日本語の「共同体」はまた違った意味合いがあるのよ。
「共同体」は、長い歴史や慣習に基づいて成り立つ人々の集団を指すんだってさ。
確かに・・・そうだね。
共同体は「生まれた時から自然に所属している集まり」という、所属は「与えられる」ことが多いイメージに対して、
外来語の「コミュニティ」は「自分の意思で参加・選択できる集まり」という観点からも、所属は「自ら選ぶ」ことが多いイメージ。
自ら所属を選択できる今の時代では、
社会や環境、自分の信条の変化に応じて、属するところを選ぶことができる。
だからこそ、コミュニティも常に変化をする生き物だと言えるんだと思う。
であれば、「コミュニティをつりたい」と願う人たちは
自分の求める理想の「コミュニティ」を具体的に説明できるようにしないと、
空中分裂する結果になることは一目瞭然だと思う。
その点、ロシアに最近誕生している新興の祖国コミュニティに学ぶ点は多い。
彼らは、自分たちのコミュニティの骨組みルールを具体的に打ち出しているからね。
そうすれば自ずとそのコミュニティに属したいか否かの選択が、誰でもできる。
たとえば、うちのコミュニティは全員ベジタリアンです、とか
うちはオフグリッドです、
といった具合。
また、この骨組み規則を厳守し、近隣住民を思いやる言動をしていれば、それ以外はほぼ自由に表現できる。
つまり、結局のところ、規則よりも「共感・実践・つながり」を大切したら、いいのかもね☆
これ、ナイスな案だと思わない?!

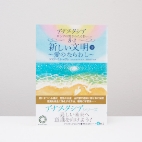 書籍
書籍
 シベリア杉のアイテム
シベリア杉のアイテム
 セレクトアイテム
セレクトアイテム






